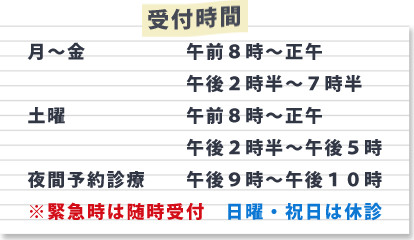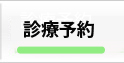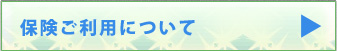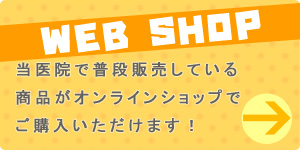ケガをしたばかりの場合
当院では、新鮮外傷(ケガをしてすぐの施術)の場合、必要に応じてアイシング療法、包帯(自己癒着包帯も使用しています。)による関節固定法、シーネとしてレナサームなどを使用した関節固定を行います。また、超音波画像診断装置による骨、筋肉の観察を必要に応じて行っています。
ケガや痛みが回復しつつあるとき
その後の回復期においては、PNF療法、モビリゼーション、電気治療(干 渉波、SSP、中周波、低周波)、遠赤外線レーザー治療(スーパーライザー)、温罨法、赤外線療法、牽引療法、ペイントルテーピング療法、キネシオテーピ ング、スポーツテーピング、各種運動療法、を用いて施術を行い、早期の疼痛緩和、外傷による腫脹(腫れ)の軽減、運動制限の改善、運動機能の改善を個々の 状況に合わせて総合的に行っています。
なお、必要に応じて顧問医への紹介、他の疾患が考えられる場合にはその専門医への紹介なども合わせて行っています。
痛みは、単に炎症による痛みだけというものではありません。
個々の心情なども複雑に絡み、心のケアも必要になりますから心のケアもご相談をさせていただきながら必要に応じて専門医をご紹介させていただき、それらを含めて総合的な施術を行い、その人にとっての早期回復を図ることが肝要です。
治りが遅い場合
ただ、治療日数が早ければよいというものでもないので、場合によっては根気よく治してゆく必要がでてくることもありま す。そんな場合に不安が生じやすくなることもたたみうけられますが、医療機関と連携をとりながらその人の症状を総合的に判断して適切な施術を選択し、場合 によっては徐々に症状緩和を促す施術がよいこともありますので、施術 期間は人によってまちまちとなります。
介護支援専門員(ケアマネジャー)の資格も取得していますので、介護も含めたご相談も気軽にお尋ねください。
用語の解説
- アイシング
-
 アイシングは、外傷後48時間ほど冷やして患部の皮下溢血や炎症が助長されることを防ぎ、痛み、腫脹の早期の改善を目的として行います。しかし、冷やし方、冷やす時間、温度などを間違えますと凍傷になる場合もありますし、シップで冷やしただけでは効果が出にくい場合もあるので、専門家にお任せいただけれ ばと思っています。
アイシングは、外傷後48時間ほど冷やして患部の皮下溢血や炎症が助長されることを防ぎ、痛み、腫脹の早期の改善を目的として行います。しかし、冷やし方、冷やす時間、温度などを間違えますと凍傷になる場合もありますし、シップで冷やしただけでは効果が出にくい場合もあるので、専門家にお任せいただけれ ばと思っています。
- 包帯
-
- 【使用目的】
関節や筋肉を圧迫しつつ固定して腫れと痛みを軽減させ、患部の安静と安定を図ります。 - 【包帯の種類】:
弾性包帯、綿包帯、自己癒着包帯(もともとは馬の脚の治療に開発されたものです。)、晒(サラシ)、三角巾があります。 - 【巻き方】:
最近では包帯を巻けない人が我々柔道整復師の中にもいるようなことをきくところですが、そもそも柔道整復師は外傷の手当てを行うプロであり、それは国家資格で認められている医業ですので、これを使う職人といっても過言ではありません。環行帯(かんこうたい)、麦穂帯(ばくすいたい)、亀甲帯(きっこうたい)、蛇行帯(だこうたい)、螺旋帯(らせんたい)、折転帯(せってんたい・・昔はゲートル巻きといっていたこともあります。日本兵が巻いていたので、高齢者の方にはご存知のかたがいらして懐かしいといわれることもあります。)などの手法を組み合わせて包帯を巻いていきます。
いずれの場合もきつすぎず、ゆるすぎず、しわにせず、関節を固定しなければなりません。
三角巾については、(公社)日本医学協会の救命講習会でも教えていますが、単に肩から腕をつるす道具ではなく、さまざまな固定の仕方を固定の場所によって変えてゆき、非常時にもとても便利に活用ができるものです。晒も裂いて使ったり、さまざまな巻き方があります。緊急時には、ポリ袋、買い物時にもらうビニール袋なども固定道具として活用できます。
- 【使用目的】
- シーネ
-
 関節を固定する簡易の副木です。昔は、金属のはしごのような形のものを新聞紙でまいてそれを包帯で巻いたものを固定肢位に合わせて作りましたが、今では、熱硬化性の樹脂を用いた再形成可能なものを使って、それぞれの人の関節やその他の部位の形に合わせてしっかりと固定できるものが使われるようになりました。当院ではレナサームなどという、熱でやわらかくしてからそれを下巻きの包帯などで保護された患部に当ててかたどりができるものを使用しています。
関節を固定する簡易の副木です。昔は、金属のはしごのような形のものを新聞紙でまいてそれを包帯で巻いたものを固定肢位に合わせて作りましたが、今では、熱硬化性の樹脂を用いた再形成可能なものを使って、それぞれの人の関節やその他の部位の形に合わせてしっかりと固定できるものが使われるようになりました。当院ではレナサームなどという、熱でやわらかくしてからそれを下巻きの包帯などで保護された患部に当ててかたどりができるものを使用しています。
- PNF
- 神経筋促通手技法という手法で、筋肉内の固有受容器といういわゆるセンサーに刺激を与えながら筋肉を収縮させる手法によって、筋肉の本来持っている機能を目覚めさせるようにしてゆく手技のことです。収縮させる手法もいろいろありますが、皮膚を介した刺激が重要なポイントになります。他のテーピングでもこの効果をうたうところがふえてきたところです。
- テーピング療法
- これも柔道整復師の得意とする分野です。
- 【スポーツテーピング】
- 捻挫の予防や再発防止の観点から、関節がスポーツしている際に必要以上に動いて傷めた靭帯や筋肉に過度のストレスが掛かりにくくするために行うものです。
- 【キネシオテーピング】
- 筋肉の代わりとして筋肉のサポートを行い、血行を良くするというのがそのうりにあっています。
- 【ペイントルテーピング】
- 私が開発したテーピング法で、幅5mmのテープを目的の筋肉、関節が促通され本来の感覚と運動状態に戻るようにPNF効果を出すことを目的として作ったものです。
- モビリゼーション
- 個々の関節を動かしながら関節の動く範囲を徐々に改善させるテクニックです。PNFと合わせて使うと効果的ですが、やはり個々の症状にあわせて使用しますので、だれにでも行うというものではありません。
- 電気療法
- いろいろな電気を使ってさまざまな施術を行いますが、つぼを刺激して血行促進をはかりながら疼痛緩和を図るSSP、深部にまで電気刺激を与えて筋肉深部の疼痛緩和と刺激による筋肉運動などを行い腫脹の早期減退を図る中周波、うねり電流を与えてマッサージ効果を出す干渉波、刺激による血行促進と皮膚表面近くの神経刺激を行う低周波、血行促進し、回復期に生じている組織損傷後の物質を早期に吸収させ治癒を促進する温罨法や赤外線、神経刺激を比較的深部に対して行うことができるレーザー治療などがありますが、やはり患者さんの相性や微妙な症状に違いに対応して使い分けを行っています。
- 来院者の社会的背景や個人的な背景
-
これが痛みを助長してしまうことがよくみうけられます。ここらのアプローチは大抵の場合、行われず、患部だけの医学的、生理学的な見地からのみ治療を行うのが普通ですが、バックグランドにある悩みを解かなければ痛みが引かないということになりかねません。そのためには、EBM(科学的根拠に基づいた治療)よりMBM(話し合いに基づいた医療)が必要な時代になってきていると感じます。その上で、適切な医療機関であったり、アドバイスなどを行いながら、その人にあった施術を選択し、患者さんとともに痛みに対応したいと思っているところです。 ちなみに当院では、アルファ21というリラクゼーションマシンも導入しています。